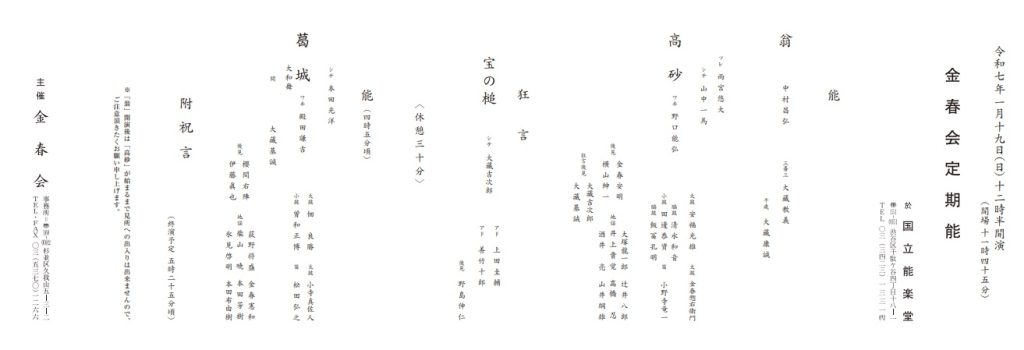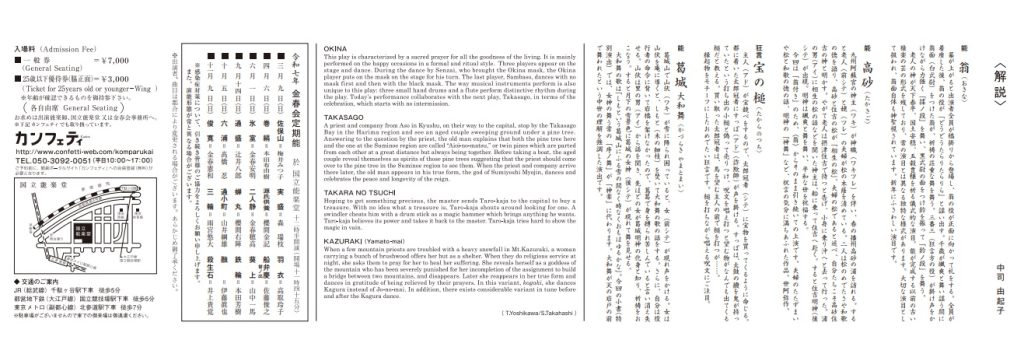2013/1/10 本田布由樹
今度の金春会では「兼平」を舞わせて頂きます。
「兼平」は修羅物と呼ばれ、源平の戦いを描いた曲の中では金春流ではあまり上演されることのない曲です。
前場があまり動きがないことや、後シテの登場がやや唐突な印象を受けること、そしてなにより「木曽義仲の最後を看取る」ということにおいては「巴」という名曲があることが理由に考えられます。
「巴」は以前舞わせて頂きましたが、女武者の華やかさと愛する人との別離、それでも自分は主君の命により生きていかなければならない・・・という明暗のはっきりとした場面展開が魅力でなるほど人気曲だなと思わされました。
その点、この兼平はいささか男臭い話です。
今井四郎兼平は木曽義仲の乳兄弟であり、有名な巴御前の兄でもあります。
義仲の最後の折、兼平は「雑兵の手にかかるよりは」と自分が時間を稼ぐ間に義仲に名誉の自害をするようすすめます。
しかし義仲は「これまで来ることが出来たのも兼平がいたからだ」と最後まで共に戦おうとしますが、ついに兼平に説き伏せられます。
自害の場所を探す義仲は、不運にも馬が深い田に落ち身動きが取れなくなってしまいます。
自分のことながらあきれ果てた義仲は、そのまま自害し果てようと思い刀に手をかけますが、ふと兼平の様子が気にかかり後ろを振り返ります。
そこに一本の矢が飛びかかり、兜の中へ突き刺さり義仲は命を落とすのでした。
そうとは知らず義仲のために時間を稼ぐ兼平。
その耳に、「義仲討ちとったり!」と敵の声が。
主君をむざむざ敵の手にかけてしまったと兼平は悔み、「これこそ自害の手本である」と叫び太刀を口に咥え、馬から飛び降り壮絶な最期を遂げたのでした。
面白いのは、「巴」では汝は女なり、と途中で故郷へ帰るように言われた巴が、今一度義仲の元へ戻るとすでに義仲は自害した後だった、という場面があること。
「兼平」でははっきりと「敵に討たれた」となっています。
兼平の「果たせなかった乳兄弟の代わりに、自分が自害してみせよう」という剛毅も、巴の「自害してしまった夫の代わりに、生きて故郷へ下ろう」という慕情も、義仲あればこそ。
兼平は最後まで、自分よりも主君である義仲を弔って欲しいと僧に頼みます。
前場では義仲にも兼平自身のことにも触れず、京都の名所教えと一仏乗の教え(天台山系の教えで、仏の真実の教えは絶対平等であり、それによってすべての人が成仏できるという考え)の話に終始します。
しかし、この仏の信仰で誰もが救われるという前場が、後の「我よりも 主君のおん後を まず弔いて たびたまえ」という兼平の健気な忠心につながっていくのかなと思います。
2013/1/10 本田布由樹